独身の高齢者はつながりを持つことが大切?!
内閣府の調査によりますと現在の日本は独身の独居者の割合が急増しているようです。2040年には3人に一人が独身になっている可能性を示唆しておりますが、2019年の現在ですら4人に一人が独身のようです。現在の日本はもはや「独…
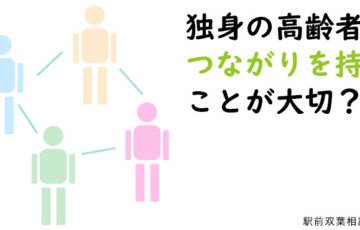 毎月更新の特集記事
毎月更新の特集記事
内閣府の調査によりますと現在の日本は独身の独居者の割合が急増しているようです。2040年には3人に一人が独身になっている可能性を示唆しておりますが、2019年の現在ですら4人に一人が独身のようです。現在の日本はもはや「独…
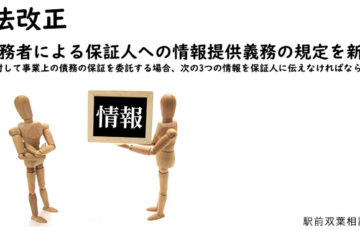 毎月更新の特集記事
毎月更新の特集記事
保証人になることを依頼される際、主債務者の財産状況等を十分に把握していないことにより、保証人になる危険性を認識せずに承諾してしまい、返済義務を負ってしまう事例が散見されます。しかし、これまでは法律上、主債務者は、自らの財…
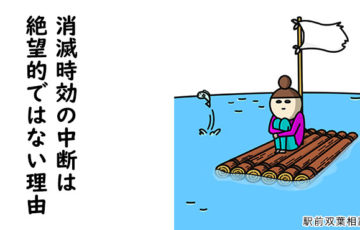 毎月更新の特集記事
毎月更新の特集記事
駅前双葉相談事務所では、開業以来多くの消滅時効の援用のご依頼をいただき、様々なケースについて対応してまいりました。そこで今回は、消滅時効の援用が利用できなかった(完成していない)ケースについて触れていきたいと思います。 …
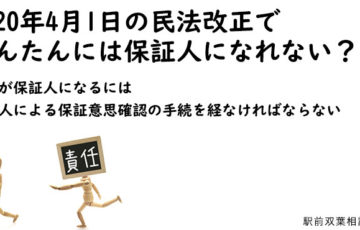 毎月更新の特集記事
毎月更新の特集記事
2020年4月1日から民法が改正されますが、その中に、 「個人が保証人になるには公証人による保証意思確認の手続を経なければならない」 という新しい制度があります。 「事業で資金が必要なので保証人になって欲しい。絶対に迷惑…
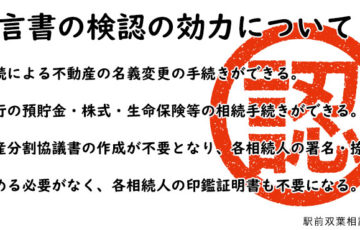 毎月更新の特集記事
毎月更新の特集記事
遺言書の検認とは? 手書きの自筆で書かれた遺言書を、遺言書を書いた方が亡くなった後に家庭裁判所に提出して行う手続きです。 遺言書の検認の効力 相続による不動産の名義変更の手続きができる。 銀行の預貯金・株式・生命保険等の…
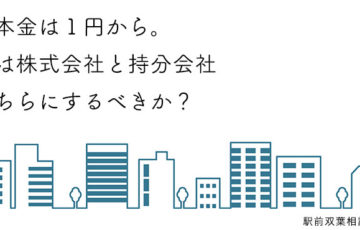 毎月更新の特集記事
毎月更新の特集記事
法人を設立するとき、株式会社か持分会社どちらにするべきでしょうか。 資本金は1円からで税制の取扱いも同じです。では、お互いの違いを比較してみましょう。 株式会社と合同会社を比較するとき、最初に大きく違いが出るのは設立時の…
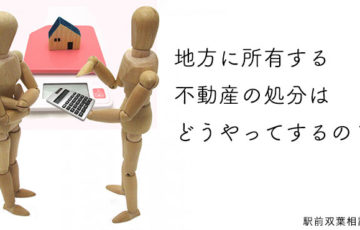 毎月更新の特集記事
毎月更新の特集記事
当事務所では不動産の売却のサポートを承っており、おかげ様でご好評をいただいております。その中でも増加傾向にあるのが、地方に所有している不動産の処分です。首都圏に在住の方は、もとは地方出身の方が多くいらっしゃいます。こうい…
 毎月更新の特集記事
毎月更新の特集記事
買戻特約とは? お金を借りるときに不動産を売る場合があります。借入が一時的なもので買戻特約をつけていれば、返済と同時に取り戻すことができます。 民法579条 民法では下記のように記されています。 “不動産の売主は、売買契…
 毎月更新の特集記事
毎月更新の特集記事
交通事故、離婚、労働問題、相続、親族の認知症の発症などのトラブルは、予測が難しく、突然身に降りかかることもあります。その状態で冷静な判断をすることは簡単なことではありません。そこで登場するのが専門家です。ではどの専門家に…
 毎月更新の特集記事
毎月更新の特集記事
農地とは? 登記上の地目が「畑」または「田」である土地のことをいいます。 農地を第三者に売却等により譲渡 農地は、宅地等と同じ手続きで譲渡することはできません。たとえ現状が宅地として課税されていたとしても、登記上が農地で…
 毎月更新の特集記事
毎月更新の特集記事
最近テレビなどで「家族信託」が注目されていますが、成年後見制度と何が違うのか気になっている方もおられるかと思います。「家族信託」とは、ご本人(委託者)の財産を、信頼できる人(受託者)に預け管理・運用をしてもらう事が可能な…
 毎月更新の特集記事
毎月更新の特集記事
不動産登記は、権利変動の流れを忠実に反映することが原則です。しかし、例えばAからB、BからCへと不動産売買があったとき、Bとしては自分に所有権移転登記をすると登記費用などがかかるため、それを省略して直接AからCに所有権移…